所在 [ 地図 ]
太田市飯田町189青田ビル3階


日常の企業活動にかかわる契約書作成、債権回収および労務問題など、地域の中小企業のご相談をお受けします
また、弁護士自身が不動産会社の取締役を務めており、不動産管理および取引についてのノウハウを十分に有しています
弁護士登録年数
顧問企業数
取扱件数
破産管財人
就任件数

高校生まで過ごした地元太田市に2008年に戻りました。
いろいろなご縁がつながり、多くの皆様からのご依頼をいただいて弁護士としての仕事を続けています。
企業が問題を抱え込まずに成長していくこと、生活の中でのトラブルを解決することに、微力ながら力を尽くしています。
最近では、事業をどうやって引き継いでいくか、または、自分の代でどうすれば終わらせることができるか、というお悩みに並走することが増えてきました。
時代の変化や世代交代の時期を迎え、製造業の集積する両毛地域ならではの課題だと思います。
何かお手伝いできることがあるかもしれませんので、お気軽にお問い合わせください。
群馬県立太田高等学校(高50回)
京都大学工学部(衛生工学)
京都大学法学部
司法研修所(56期・仙台地裁配属)
鹿野法律事務所(現・鹿野森田法律事務所)
せせらぎ法律事務所
弁護士法人せせらぎ法律事務所(群馬弁護士会所属)
日頃取り扱う業務の一部をご紹介いたします
業務にあたっては、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士など隣接士業との協力および不動産事業者、金融機関とも連携し、最適な解決手段を提供できる体制を構築します
法人の破産申立を行うほか、連帯保証人について経営者保証ガイドラインの活用や個人再生、不動産の任意売却など様々な手続を組み合わせて、ご自宅等を守る手立てを考えます
労災事故、未払残業代、ユニオンからの団体交渉など、不意に起きる労務問題について、その予防または対処に最善を尽くします
パワハラなどの見極めの難しい懲戒事案の調査も行います
賃料未払い、入居者の高齢化、借地の返還に伴う不安など、賃貸物件の管理にまつわるあらゆる相談に応じます
紹介できる不動産業者も各地域にありますので、売却事案の取り扱いも可能です
群馬県事業承継・引継ぎ支援センターに専門家登録されていますので、多数の事業承継・M&Aのサポート、契約書作成の経験があります
遺言書の作成、事業承継対策、遺産分割交渉または調停、相続放棄など、相続に関係する業務も多く扱っております
公開できる範囲でこれまでの活動をご紹介いたします
・小暮建設株式会社
・株式会社エムアンドシー
・株式会社イスズテックス
・株式会社ナガヌマ
・株式会社マルヤマ ほか
会社の破産申立にあわせて、連帯保証人の債務を経営者保証ガイドラインを利用して債権放棄を受けた事例
これまでに3件。いずれも自宅を確保
弁済率1%~10%
千代田町インドフェスタin光恩寺(2023-)を実行委員会の副委員長として企画・開催。2024年には約5000人を集客

・社会福祉法人(子ども園)苦情解決のための第三者委員
・都市計画法に基づく再開発事業の審査員
・太田ロータリークラブ会員
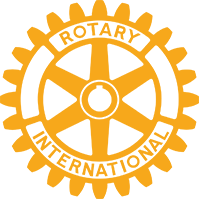
関東学園大学(地域経済デザイン論)、千代田町介護特別講座(お金のトラブル)、職業紹介授業(市立太田、県立太田)での講演
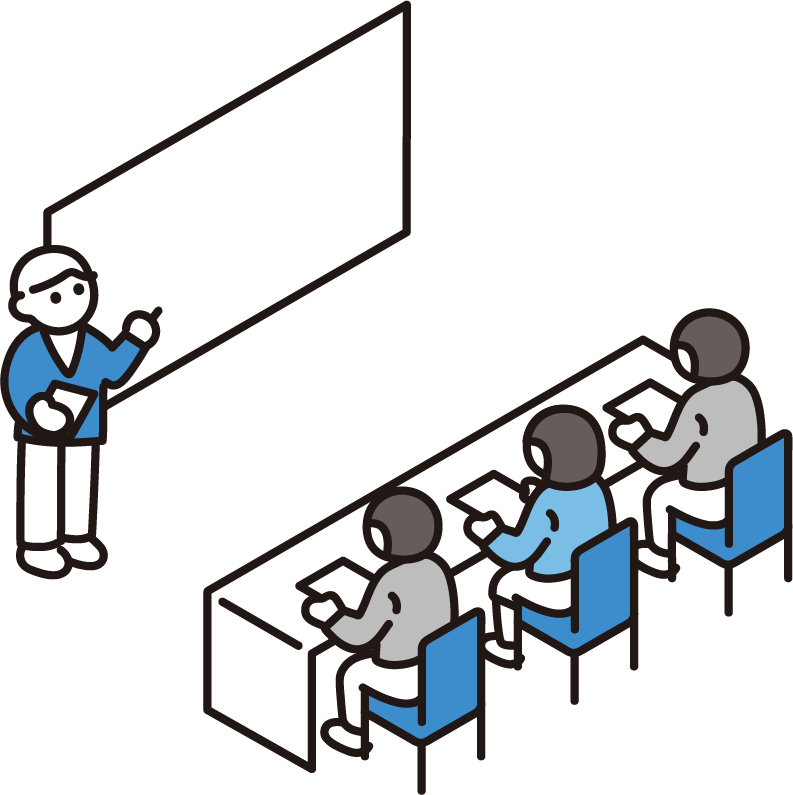
ご予約・お問い合わせは、お電話でお願いいたします。営業時間は平日9時~17時
営業時間は、平日9時~17時です。